- ラダックでテント泊トレッキングに挑戦してみたい
- 標高5000mを歩いてみたい
- 人が少ないトレイルを歩きたい
そんな方には今からご紹介する
- ルムツェからツォモリリを歩くトレイル(Rumtse to Tso Moriri Trek)
がオススメです。
ラダックエリアで有名な湖のツォモリリへ歩くトレイルです。
本記事では分かりやすくツォモリリトレックとしてご紹介します。
それではいきましょう!
目次
ツォモリリトラックとは

ラダックエリアの南東部(ムプシュ地方)にある有名な湖・ツォモリリを目指すトレイルです。
途中、もうひとつの湖であるツォカル(Tso Kar)を見ながら歩くことができます。
標高は4000mから5500mに及び、高度順応は必須となりますが、景色は圧巻です。
トレイル自体は難しくないですが、テント泊必須のトレイルとなっており、個人では難易度が上がります。
実際に著者もツアーを利用して歩きました。トレイルレポートは別記事にまとめています。合わせてご確認ください。
ツォモリリトラックの特徴

次にツォモリリトレックの特徴について4点お届けします。
- 標高4500−5500mの圧巻の景色が続く
- 湖を2つ見ることができる
- 1週間テント泊必須のトレッキング
- ルートファインディングや渡渉など登山スキルが必須
ひとつずつ確認しましょう。
ツォモリリトレック特徴①:標高4500−5500mの景色
まず大きな特徴が標高が高いということです。
スタート地点のルムツェで標高は4200mを超えています。
そして宿泊は4500mから5000mの所で過ごします。
最高標高はYalung Nyau La の5530mです。
そのため、高度順応できていることが必須となります。
ラダック地方やネパール等ですでに順応できている方は、すぐに歩くことができるでしょう。
私はレーに1ヶ月滞在。マルカバレートレック等歩いて順応できていましたが、それでも登りは息切れして苦戦しました。
高山病対策については別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
ツォモリリトレック特徴②:湖を2つ見ることができる
ツォモリトレックのもうひとつの大きな特徴が、湖を見るトレッキングということです。
ラダックエリアのトレッキングは多くが谷底を通り、川のそばを歩くトレイルは多いです。
しかし湖を見るトレイルは少ないと感じました。
(有名な湖・パンゴンツォは観光で行く場所であり、トレッキングルートはありません。)
ツォモリリトレックで見ることのできる2つの湖は、氷河が溶けた水や石が流れ込み、美しいコバルトブルーの色をしています。
是非その目で美しさを味わっていただきたいです。
ツォモリリトレック特徴③:1週間テント泊トレッキング
ルムツェからツォモリリへ歩く場合、基本的に6泊する必要があります。
村があるのは3つ
- スタート地点のルムチェ
- ツォカル湖畔(トレイルからは離れている)
- ゴール地点の村カルゾク(ツォモリリ近郊)
しかありません。
道中では全てがテント泊と思った方がいいでsしょう。
水の補給はできますが、食料補給はできません。
個人で歩く場合は全ての食料を持ち運ぶ必要があります。
ツアー参加の場合、コックやポーターが同行するため、日帰り装備の荷物を持って歩くことができます。
ツォモリリトレック特徴④:登山スキル必須のルート
ツォモリリへ続くトレイルは岩場などは少なく、ルート上に難易度が高い箇所はありません。
しかし標高が高く、毎日のように峠越えがあります。
標高の高さから、夏でも夜は5度以下となり充分な防寒対策が必要です。
また、個人で行くとルートファインディングがとてもとても大変!です。
歩いているハイカーは他のトレイルと比べると極端に少ないため、一旦道に迷うと遭難となることも。
そして時期によりますが、靴を脱ぐ渡渉が多いです。
よほどの登山スキルがある方以外は個人でのトレッキングはお勧めしません。
(実際に個人で歩いた方とお話ししましたが、危険な経験をしたと言っていました。)
公共交通機関も整っていないため、ツアーを利用した方が良いでしょう。
ツォモリリトラック:トレイル詳細

次に、ツォモリリトレックの詳細についてお届けします。
ツォモリリトラック:トレイル概要
- 距離: 92.5km
- 日数:7-8日間
- 難易度:★★★★★
- 最高標高:5,435m
- 宿泊:テント
ツォモリリトラック:スタート・終了地点
- 開始地点:Rumtse
- 終了地点:Korzok (Tso Moriri)









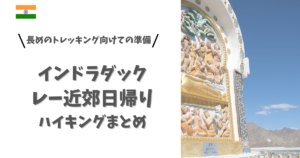
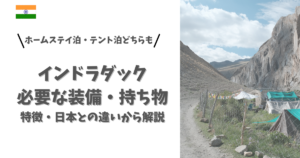

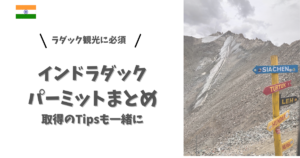
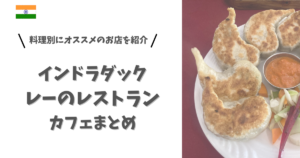
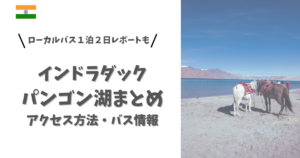


コメント