- 海外に行ってみたいけどど何もわからない
- 海外トレッキングをしてみたいけど初めての海外で不安
本記事はそんな方に向けて、海外旅行の際に準備することを徹底的にまとめました。
下記のフローチャートで考えるようにしましょう。
- 準備前にまず考えること
- 具体的な準備方法
- その他の準備(プラスα)
①について回答ができる場合、②からスタートしても大丈夫です。
準備について全てまとめましたので、文字数6,000字以上の大ボリュームとなりました。
特に初海外の方はしっかり目を通してくださいね!
それではいきましょう!
海外旅行準備:準備前にまず考えること
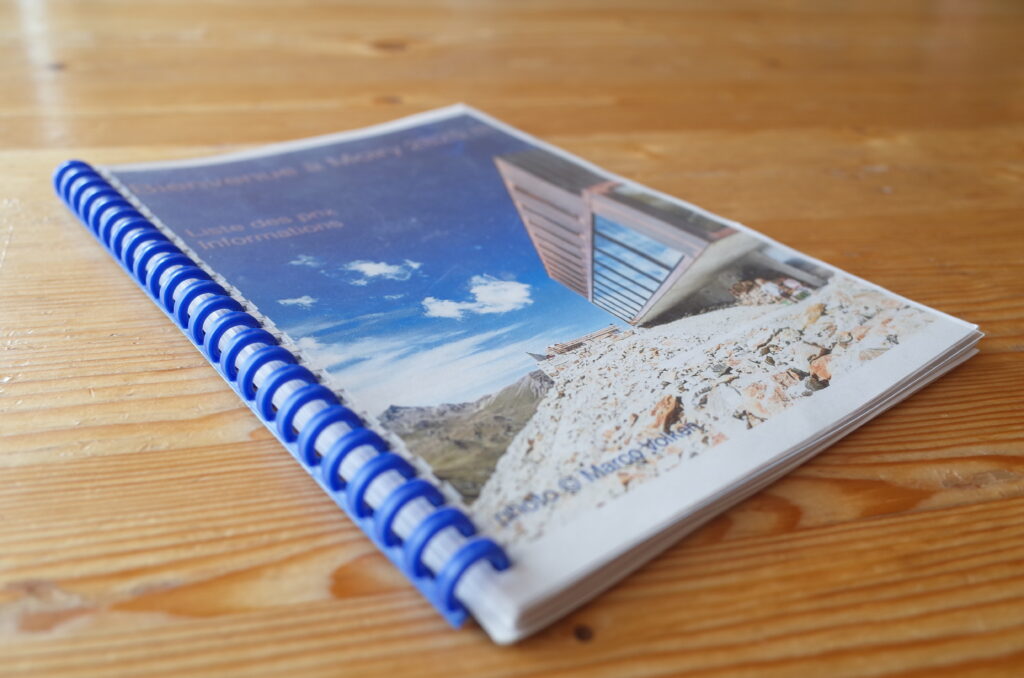
まずは旅の方向性を決めます。
具体的な準備に取り掛かる前に、まず下記6点についてしっかり考えましょう。
- なぜ行くのか
- どこへ行くのか
- 誰と行くのか
- 旅のスタイル
- いつ行くか
- 予算はいくらか
①:なぜ行くのか
まず最初に最も大切なことを考えます。なぜ行くのか、「旅をする理由」を考えましょう。
自分がこの旅に興味を持ったきっかけを振り返って言語化してください。
「このご飯が食べたい」「トレッキングで日本にない景色をみたい」など、なんでもOKです。
パッと出てこなくても大丈夫です。曖昧な理由でもいいので、まずは自分の頭で考えてみましょう。
個人的にこの「旅のキッカケ」を言語化しておきたいのには訳があります。
それは自分で軸の部分が確認できていれば、間違った選択をしないからです。
実は旅って毎日が決断と選択の連続です。時には甘い誘惑があったり、悪いことに巻き込まれることもあります。
ノリと勢いでなんとかなることもあるかもしれません。
しかし私は、このブログを読んでいる方にできる限り最良の判断をして欲しいのです。
旅の目的や軸が常にご自身の中にあると、何かあった時にきっと役に立ちます。
②:どこへ行くのか
次にどこへ行くかです。通常、1カ国の旅行の場合は、①とセットで考えていきます。
またこの国のどの場所に行きたいのかまで、具体的に書き出してみましょう。
観光地やトレッキングルートまで書き出すと、より明確になります。
またやりたいアクティビティについてもあれば書き出してOKです。
数カ国周遊する場合でも、初めの段階で自分が行きたい国をリストアップしておきましょう。
長期間旅に出る場合は、道中で予定が変わることがあるので、臨機応変に対応できるようにしましょう。
③:誰と行くのか
次に誰と行くのかです。ひとりで行くのか、家族で行くのか、カップル2人旅、友人と行くなど、誰と行くのか考えましょう。
ひとりで行く場合、当たり前ですが全て一人で準備する必要があります。
友人やパートナーと行く場合は、行きたい場所のすり合わせや、準備の役割分担などあるでしょう。
しかし、一人ひとり当事者意識を持たないといけません。誰と行っても人任せにはしないのが海外旅行です。
また、途中で友人と合流、この時だけ一人など具体的にあれば、それも一緒にイメージしましょう。
私は、海外一人旅から友人との旅行、家族で行く海外、グループ旅行など、様々なかたちで海外旅行の経験があります。
どれが良いという訳ではなく、優劣はありません。一人でも誰と行っても楽しいです。
しかし、誰と行くかで次にご紹介する旅のスタイルは変わってきます。
④:旅のスタイル
次に旅のスタイルです。私は大きく3つに分けられると思います。
- お金をかける豪遊スタイル
- バックパッカー貧乏スタイル
- 豪遊はしないけど一点にお金をかける中間スタイル
です。
これらは行く場所や誰と行くかによって変わります。
一生に1回の新婚旅行や両親と行く家族旅行なら、豪遊スタイルが多いでしょう。
また、一人で治安の良い北欧にバックパッカースタイルでトレッキングをするもあるでしょう。
3つ目の中間スタイルは
- 基本はバックパッカースタイルだけど宿はお金をかける
- バックパッカースタイルだけどクルーズ船にはお金をかける
- 移動はビジネスクラスを利用するけど食事と宿は節約する
などです。
私は一人旅の際はバックパッカースタイルが多いですが、時に中間スタイルになったこともあります。
旅のスタイルやお金をかけるポイントは一人一人違います。
その後の予算などにも関連するので、早めに考えておきましょう。
⑤:いつ行くのか
次にいつ行くかです。基本的にその場所のベストシーズンに行くことをお勧めします。
複数の国を行く際は、それぞれベストシーズンに行けるように予定を組んでみましょう。
また、ベストシーズンにもデメリットがあります。
多くの観光客やハイカーが殺到するので、宿泊施設が予約できない・パーミットが取れないなど、弊害があります、
その際は、少しハイシーズンからずらしてみましょう。
観光の場合、早めのシーズンでも遅めのシーズンでもどちらでもお勧めです。
例えばカナダ観光の際、早めのシーズンに行くと山々に雪が残っており綺麗です。遅めシーズンでは黄葉を楽しむことができます。
トレッキングの場合、個人的に時期をずらすなら遅めのシーズン・シーズン終わりがお勧めです。
早めのシーズンなら、雪がまだ残っている可能性があり、トレッキングに制限がかかることが多いからです。(もちろん遅めでも雪などのリスクはあります。)
⑥:予算はいくらか
最後にだいたいの予算を決めましょう。
これは行く場所・旅のスタイルや行く時期・期間によって大きく変わります。
そのため最後に考えましょう。
予算は最初は細かく計算せず大まかで大丈夫です。
例えば私の場合、このように予算を組んでいました。
コロナ前の円高時バックパッカースタイルで、新興国1日3000円、先進国1日6000円です。(航空券代別)
今は個人的にこの金額での旅行はできないですが、人によっては今でも可能でしょう。
長期の場合はバックパッカースタイルで1年250万で考えていました。
実際に円安の今では、一人旅中間スタイルで2ヶ月100万くらいの予算で考えています。
アジアのみなら節約しなくても2ヶ月50万程度です。
また参加するツアーやアクティビティでも変わってきます。
予算が決まり、予算に対して手持ちのお金が不足していれば、お金を稼ぎましょう。
予算はあくまで目安なので、不測の事態に備えて多めに蓄えておいた方が安心です。
実際に海外旅行の準備を始める

上記について旅の方向性が決まったら、具体的に準備を始めていきます。
準備は「①(継続)→②→③④⑤→⑥」で進めていきましょう。
- 情報を集める
- パスポート取得・有効期限を確認する
- 航空券を取る
- ビザを取る
- 宿泊施設やツアーを予約する
- 海外旅行保険に入る
①:情報を集める
まずは情報を集めます。情報源は様々ありますが、自分の得たい情報が見つかるまで根気強く調べましょう。
日本語での情報が少ない場合は英語でも調べるようにしましょう。
下記に情報源の一例を挙げます。
- 本・ガイドブック
- インターネット(ブログ・YouTube)
- SNS(X・インスタ)
- 旅行者から直接聞く
- 旅行中の宿泊施設から
日本にいる間は本やインターネットがメインで情報を得ます。(このブログもそんな皆様のお役に立てるように頑張ります!)
この情報集めは現地に着いてからも継続します。
実際に行ってみるとより最新の情報が手に入ることもあります。
また旅先では旅行者やハイカーと積極的に交流し情報交換するようにしましょう。
②:パスポートの取得・有効期限を確認する
次にパスポートについてです。
パスポートは海外であなたの身元を証明できるとても大切なものです。
持っていない方はすぐに取得しましょう。
またパスポートの有効期限が迫っている方は確認が必要です。
国によっては「パスポートの有効期限が半年以上あることが入国条件」というところもあります。
有効期限が迫っているときは早めに更新する方が無難です。
パスポートについては別記事でまとめています。合わせてご確認ください。

パスポートオンライン申請についてはこちらの記事でご確認ください。
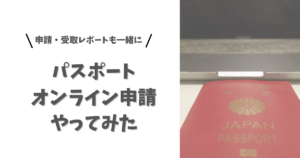
③:航空券を取る
次に航空券の取得です。
航空券は旅の日程が決まればできるだけ早く予約した方がいいでしょう。
場合によっては予約時にパスポート番号が必要です。
ビザは当日搭乗時には確認されることもありますが、予約時に番号を売れることはまずないです。
航空券は予約については
- 比較サイトで価格比較 → 直接ホームページから購入 or 予約サイトから購入
がいいでしょう。
オススメ予約サイトはエクスペディアとTrip.comです。
具体的な航空券の予約方法については別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
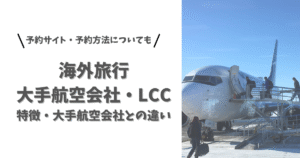
④:ビザを取る
次にビザについてです。
ビザはそれぞれの国が旅行者に発行される入国許可証です。
国によって違いがありますが、多くは事前にオンライン申請が可能です。
また、日本にあるその国の大使館でビザを申請することもあります。
今は大使館に行って取得申請をすることはほとんどなくなりました。
しかし、アメリカの3大トレイルのスルーハイク等、長期で同じ国にいる場合は注意が必要です。
例えばアメリカは3ヶ月以内の滞在であれば、観光ビザは免除され、電子渡航認証のみ申請すれば大丈夫です。
しかし、ロングトレイルのスルーハイクの場合、3ヶ月以上滞在が必要です。
3ヶ月以上滞在していると不法滞在となるので、事前に観光ビザを3ヶ月以上取得しておく必要があります。その場合、大使館へいくことになります。
- 自分がその国にどのくらい滞在するか
- その国が日本人に対してビザを必要としているか
- その国のビザの申請方法がどのようなものか
整理しておきましょう。
ビザについては別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
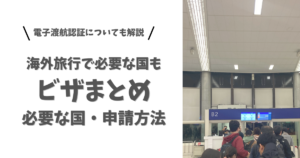
⑤:宿泊施設やツアーを予約する
航空券が取得できたら宿泊施設やツアーを予約しましょう。
また現地で移動するバスや電車についても、具体的な日程が決まっていれば予約しましょう。
ハイシーズンの人気観光地は、条件の良い宿泊施設から予約が埋まっていきます。
特に山岳リゾート地で宿泊施設が少ない街は、できるだけ早く予約しましょう。
私が一番利用する予約サイトはBooking.comです。
【Booking.com】ツアーに関しては個人的に焦る必要はないです。
特に日程に余裕がある方で、現地発着の日帰りツアーの場合、予約がギリギリになっても可能な場合が多いです。
(もちろん、日程が決まっている方は早めの予約にこしたことはないです!)
私の現地ツアーのおすすめはベルトラです。場所によっては個人で行くより割安に行けることもありますよ!
Veltra Top Page具体的な宿泊施設や現地ツアーの予約サイトについては別記事でまとめています。合わせてご確認ください。

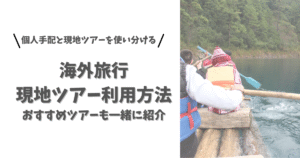
⑥:海外旅行保険に入る
最後に海外旅行保険に入りましょう。
海外旅行保険はクレジットカード付帯でも保証が可能な場合があります。
個人的にクレジットカード付帯ではまかなえない場合、別途海外旅行保険に入ります。
- クレジットの保証内容が不安な場合
- 旅行が長期の場合(3ヶ月以上)
- 治安の悪い国に行く場合
- 高山病のリスクがある場所に行く場合
上記に当てはまるときは別に海外旅行保険に入ることをおすすめします。
私は旅中に病気や盗難など様々なトラブルを経験しました。その度に海外旅行保険には本当にお世話になっています。
海外旅行保険は旅する上でお守りのような存在です!万が一に備えてしっかり入るようにしましょう!
私は旅のトラブルも多いので、、海外旅行保険の利用はクレジット付帯の保険も含めて何度も経験があります。(いらない経験ですが)
海外旅行保険については別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
プラスアルファの海外旅行準備

最後にプラスアルファの準備についてです。
全ての人に必須ではないけど、該当する方は早めに準備する必要があります。
- パーミットを取得する
- 予防接種を受ける(新興国・長期旅行必須)
- 持ち物の準備
- 会社を辞める前にすること
- 語学の勉強
①:パーミットを取得する
まずはパーミットの取得についてです。
パーミットとは、そのエリアやトレイルを歩く時に必要な許可証です。
観光の方にとって事前準備の必要はないですが、アメリカを歩くハイカーはほぼ必須です。
アメリカの一部ハイキングコースなどはパーミットを半年前に取得しないといけないものがあります。
- アメリカのトレイルはビザよりも航空券よりもまずパーミットです!!!
パーミットがないと目的を達成することができません。
またネパールやラダックのパーミットについては現地に到着してから取得が可能です。
各トレイルによって違うので、しっかり情報を確認しましょう。
②:予防接種を受ける
予防接種については渡航する国で打つ種類が変わってきます。
日本では終息している疾病でも、他の国では発病するリスクがある疾病は沢山あります。
行く国の情報をしっかり調べて、必要な予防接種をしましょう。
- 長期旅行
- 新興国
へ行く場合は予防接種は必須となります。
長期旅行や世界一周の場合、必要な予防接種は
- 狂犬病
- 破傷風
- 黄熱病
- A型肝炎
などです。
予防接種については別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
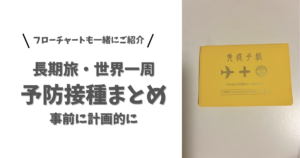
③:持ち物の準備
海外旅行や海外トレッキングで使用できる持ち物を準備しましょう。
また、クレジットカードやSIMカード・ポケットWiFiなども必要に応じて用意しましょう。
持ち物やクレジットカードについては別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
④:会社を辞める場合、退職前にすること
世界一周やワーキングホリデー・ロングトレイルを歩く場合、会社を退職することがあります。
会社を退職する際は退職前に知っておくべきことがあります。
- クレジットカードを作る
- 海外転出届を出すか考える
クレジットカードは会社員である方が審査に通りやすいです。
もし海外で使いたいクレジットカードを持っていない場合、退職前に作成しておきましょう。
クレジットカードのオススメはエポスカード!!
年会費無料で利用付帯の海外旅行保険の補償が手厚いです!(実際にエポスカードの保険を利用したこともあります!)
クレジットカードについては別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
また1年以上日本を離れる場合、海外転出届を出すことができます。
海外に転出した場合、住民税や国民健康保険を免除することができます。(年金も免除可能・追納もできます。)
詳細については別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
⑤:語学の勉強
言語が分からなくてもボディーランゲージでなんとかなる。
しかし少しでもその国の言語が話せると、旅がより濃厚なものに変わること間違いなしです。
少なくとも英語は少し話せる方がいいです。
語学に不安が残る場合は、日本にある間に語学の勉強をしましょう。
英語の場合、様々なオンライン英会話があります。
多くの場合、マンツーマン指導で必要な状況を設定してくれるため、より実践的な英語が身につきます。
他の言語についてはyoutubeや言語学習アプリがおすすめです。
言語学習については別記事でまとめています。合わせてご確認ください。
まとめ:旅立つ前にしっかり準備しよう
海外旅行に行く際の準備について徹底解説しました。
初めての海外旅行や海外トレッキングの際に大いに役立ててください。
本記事が今後海外旅行に行く方のお役に立てば幸いです。
素敵な旅を♪




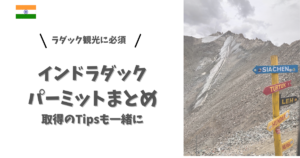
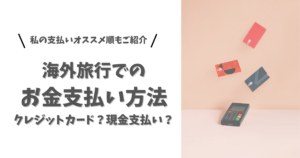
コメント